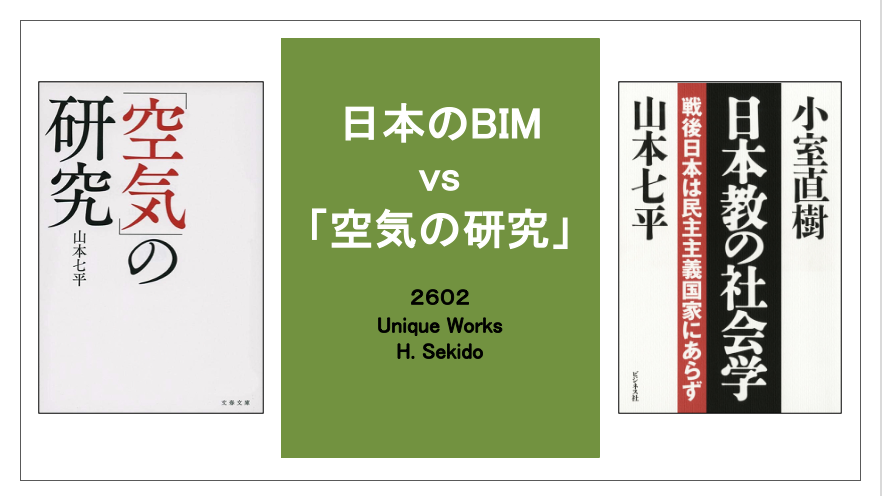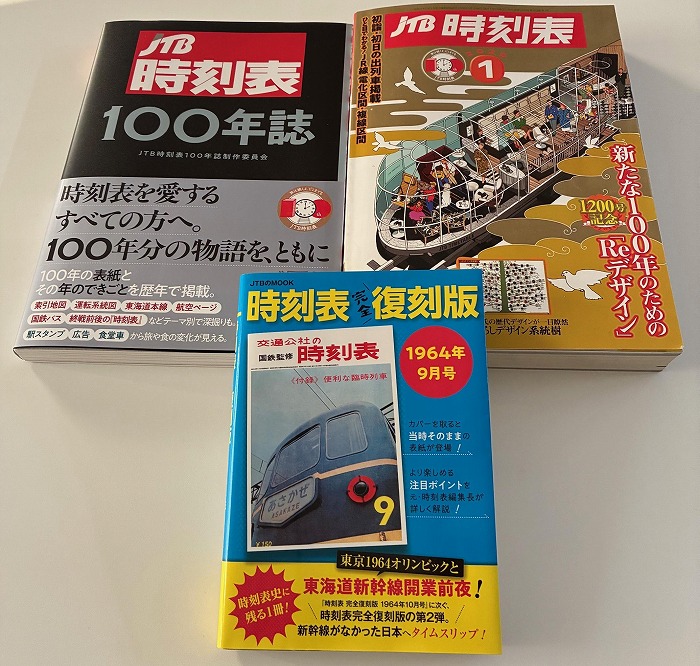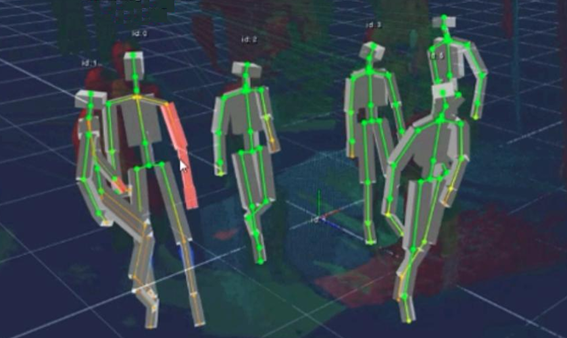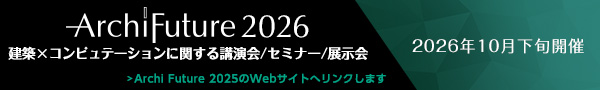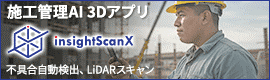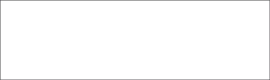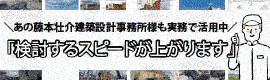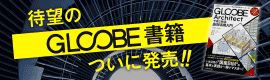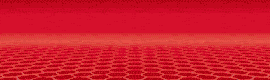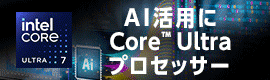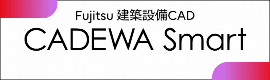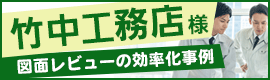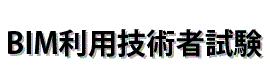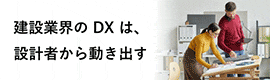![]()
BIMを技術のための技術にしないために
2025.05.20
パラメトリック・ボイス 前田建設工業 綱川隆司
前回のコラムの続きで自動車の話から始めます。BIMの話に戻ってくるつもりですのでもう少
しお付き合い下さい。引き続き厳しい状況の日産ですが北米のハイブリッド車の戦略が課題で
あったと言われています。シリーズハイブリッドと呼ばれるパワートレインを様々な車種に適
用していますが、これはざっくり言うと駆動力は電気モーターに任せてガソリンエンジンは発
電のみを行うもので、一般的なハイブリッド車より電気自動車に近い仕組みです。ストップ
アンド ゴーの日本の道路事情には適していて人気があるのですが、高速走行時の燃費が他の
ハイブリッド方式ほど伸びないらしく、北米で受け入れられなかったようです。
優れた技術やプロダクトであっても社会や市場から支持されなかったものは他にもあります。
記憶に新しいところでは3Dテレビでしょうか。2010年頃に発売されていましたが気がつくと
店頭から消えていました。大きなものでは超音速旅客機のコンコルドは画期的な旅客機でした
が燃料コストや騒音問題、運行費の高さから商業的に持続できず、2003年を最後に27年間の
幕を閉じました。スペースシャトルは再利用できる宇宙機として135回打ち上げられましたが
2011年を最後に退役し、後継機も作られていません。当初1200万ドル/回と言われていたコ
ストは、途中コロンビア号の事故も挟み10億ドルまで膨れ上がったともいわれています。
「技術のための技術」という言葉があります。技術自体が目的となり、社会的な有用性や経済
的な価値よりも技術的な進歩や知識の深化自体を目的とする概念です。これを技術至上主義と
批判することは危険かもしれません。しかし「技術」が課題解決や市場のニーズに応えること
が出来ない場合に自然淘汰されるのならば、そこにも生存戦略が必要なのかもしれません。
ここで今回のタイトル通りBIMに触れることについては正直気が重いのですが、今世紀初めに
「建築で3DオブジェクトCADなど幻想」と言われていたことも思い返しながら、BIMを技術
のための技術にしないために、今回三つの要素を考えてみます。
①感性品質:利便性と使い心地
ユーザーがそのツールを日常的に使いたいと思い続けることは、実はハードルが高いと思い
ます。自動車においても一つのペダルで加減と減速を行える「ワンペダル」の機能がありま
したが、操作感が従来のアクセルペダルと異なるためかあまりユーザーからは支持されな
かったようです。映画やTVの3Dメガネの着用もこれまでの視聴体験とのギャップが大き
かったのではないでしょうか。
BIMについて、私自身アプリケーションの使い心地には拘ってきました。四半世紀前はハー
ドの性能が低いことに起因する処理の遅延は大きなストレスでした。2025年の現在はグラ
フィックボード入りのノートPCをメインマシンにしており、2kg超えの重量はカバンに入れ
ると腰にきますが、先のストレスはかなり軽減されました。今回の気づきはアプリケーショ
ン操作感や使い心地も、それが選ばれる理由としては大きいのではないかと言うことです。
②価格の妥当性: 機能とベネフィット
一言でいえば、ユーザーが払うコストに見合う見返りが得られるかどうかです。ハイブリッ
ド車自体は決して安くはないと思いますが、BEV(電気自動車)が出てきた今でもユーザー
の価値観によるとは思いますが市場からは支持されています。
3Dテレビはハードがハイエンドモデルとなりがちで高価であったのも廃れた理由かもしれ
ませんが、当時の映画の「アバター」のような魅力的な映像コンテンツが連発していればも
しかすると状況は変わったかもしれません。
BIMについては導入時の環境整備だけでなく教育にもコストが必要ですし、導入後のメリッ
トを定量的に評価することの難しさは携わった方誰もが感じたことではないでしょうか。
③移ろう環境:エコシステム
BEVも充電インフラやバッテリー寿命等の課題があり、国内では2023年の新車販売で2%に
も満たない状況であり普及は順調とは言えないと思われます。各自動車メーカーは完全電動
化のマイルストーンを一度は掲げましたがその後に続々修正しました。さらに中国の新興
メーカーとの競争にも晒されています。将来的には化石燃料が枯渇する(2060年代?)の
で全てのハイブリッドシステムは言わば繋ぎの技術かもしれませんが、日本の基幹産業と言
われる以上はサプライチェーンやエネルギーインフラと合わせて国家戦略レベルの話にもな
ります。
BIMについては今後サプライチェーンへの普及や自動施工等が浸透すれば必須とされる技術
なのは違いありません。ただ事業主側や社会全体を巻き込んだSociety5.0やデジタルツイン
を考えた場合に求められるBIMは、現在ゼネコンが必死に入力しているものよりはもっとミ
ニマルなモデルかもしれません。
また持続可能性を考えたとき、ハードメーカー・ソフトメーカー・ユーザーの間で相互に支え
合うエコシステムであるべきと思いますが、ソフトウェアのサブスクリプションの金額が右肩
上がりなのも気になります。円安と言えばそうなのですが・・・。
BIMが後世に「技術のための技術」として語られることが無いよう、まずは目的を手の届く範
囲で明確にすることが重要だと思います。明確な実用性や経済的な持続可能性が不明確なまま
で可能性のみを追求することは学術的な意味はあれど、一企業として或いは業界全体としても
大きなリスクがあると言えそうです。

写真は愛車のメーターパネル。デジタルなので情報量が多く、かつ
レイアウトまで変わるのは驚きです。別に壊れなければアナログで
もいいのですが。3ペダルHパターンシフトが淘汰されず、まだ新車
で買える時代で良かったです。