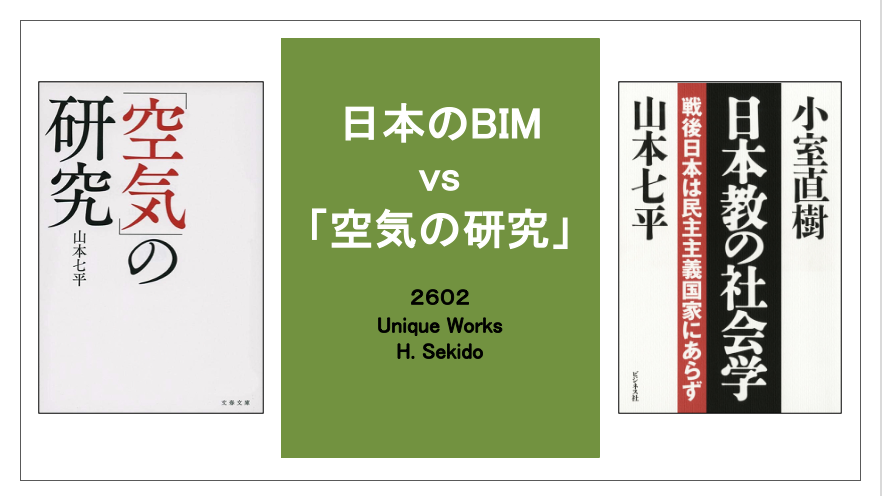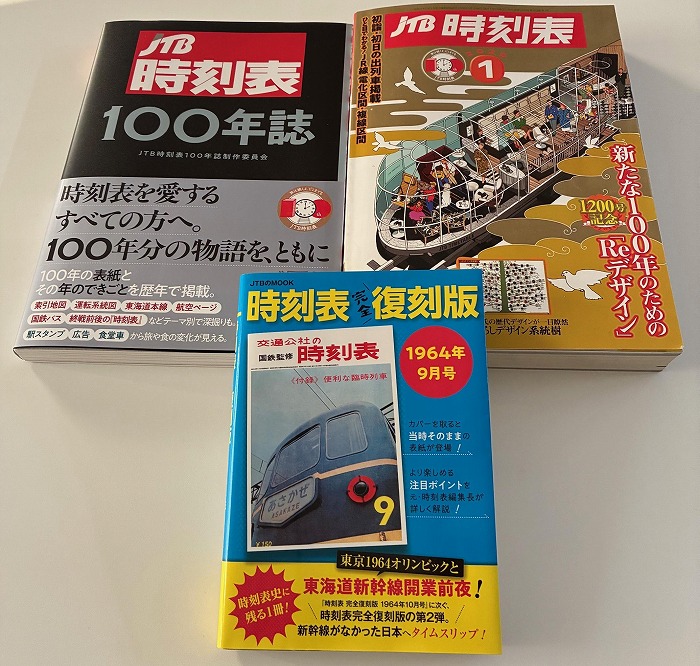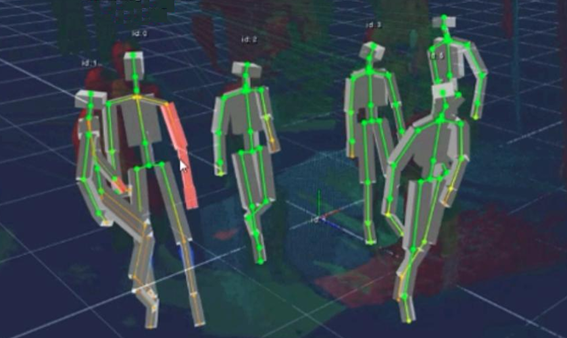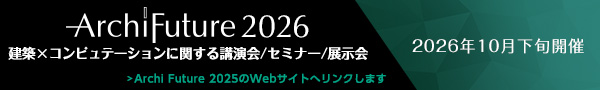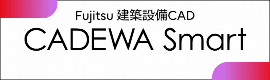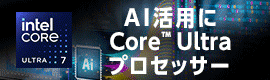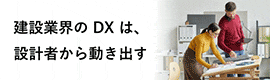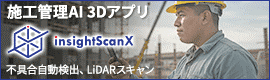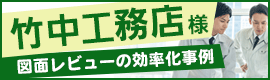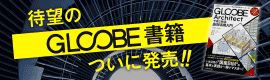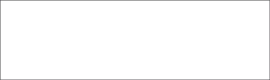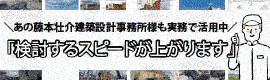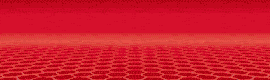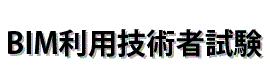![]()
ライフサイクルBIM10
~現況BIMを中心とする建物データリポジトリ
2025.05.22
パラメトリック・ボイス NTTファシリティーズ 松岡辰郎
建物ライフサイクルマネジメントにおける建物データの活用は、建物の状態・状況をさまざま
な業務の視点から参照するものと、既存の建物に何らかの変更を加えるための元情報として引
用するものに大別される。建物はさまざまな部位・機器で構成されていることから、その形状
とそれらがどのような特徴や性能諸元を有しているかを、それらを統合したBIMモデルで建物
データ化することは改めて考えてみても理にかなっているだろう。このような観点から、筆者
が所属するNTTファシリティーズでは既存の情報通信施設を対象とした建物ライフサイクルマ
ネジメントにおいて建物の現在の状態を現す「現況BIM」を整備し、各種の業務で参照すると
ともに、改修等における設計の基盤データとして利用し、建物の変更に応じた現行化を続けて
いる。現況BIMは最も長いもので運用期間が5年以上となり、その間の建物の変更に応じた現
行化と更新も多いもので20回を越える。色々な残課題はあるが、適正に現行化を続けること
で、建物ライフサイクルマネジメントにおける建物情報活用の原本として利用できている。
現況BIMは建物ライフサイクルマネジメントやFMで利用する建物情報の中心的な存在である
ことは疑いの余地がない。とはいえ、業務の内容や目的によっては現況BIMのみでは必要な建
物情報が網羅されないこともまた事実だろう。
建物を新築し、竣工時に設計施工に加えて運用・維持管理に関する情報を追加した竣工BIMを
受け渡すことで、完成時の建物情報は運営・維持管理工程に継承される。建物の物理的な性能
の維持のみに着目した新築の竣工時であれば、このようなデータフローで建物情報を扱えば良
いだろう。しかし、建物を経営資源や事業ツールとして捉える場合、現況把握と分析評価やそ
れに応じた運営方針の策定および用途変更で改修や模様替え等が発生することを考慮すると、
参照すべき建物情報の種類と範囲は大きく広がる。
運営中の建物に対して改修を行う場合、当然のことながら建物の内部には建物オーナーやユー
ザーが所有・使用しているさまざまなモノが置かれている。そして、これらは建物を改修する
際に設計に影響を与えることとなる。ところが一般的な建築図面にはこれらの非建築情報は含
まれていない。現況BIMも同様のため、それのみでは適正な改修設計は容易ではない。もちろ
ん実際の改修設計時には現地調査を行い、建築と非建築の両方について現状を把握することに
なる。しかし、距離的に遠い場所や行くことが容易ではない立地条件、建物の運営上から現地
調査の時間に制約があるものも少なくはない。そのためには最初の机上検討段階でなるべく多
くの情報を取得し、より精緻な現状把握をしておきたい。
現況BIMに含まれないモノを簡単に把握する手段はいくつかあるが、比較的容易に情報を整備
構築できるものとして、画像情報をあげることができる。とはいえ、さまざまな立場・業務・
視点で撮影した画像を体系的に管理・共有するのは思うほど簡単ではないこともわかってきた。
建物ライフサイクルマネジメントにおいては現況BIMと同様に、すべてのステークホルダーが
共有できるような建物情報を整備する必要がある。そこで、現況BIMを補完する情報として、
パノラマカメラによる全天球画像の組織的な整備を行うこととした。特定のものを注視して撮
影する通常の画像と比較してより広範囲かつ俯瞰的・客観的な情報となる全天球画像は、ある
程度以上の解像度や画像品質を確保すれば、異なる業務間で画像情報を共有できそうだという
ことがわかった。ただし、建物内外における撮影位置や撮影高さといったものを規約化しなけ
れば、さまざまな立場で建物情報として活用することは困難となる。また、継続的に全天球画
像を活用していくには、死角のない撮影ポイントの決め方、劣化の進行を定点観測する長年に
わたる同位置での定期的な撮影方法、多数の画像情報の管理手法といった様々なルールの設定
とノウハウの確立が必要となる。現況BIMを補完する情報として点群データの活用も期待でき
るが、強力な磁力線を出すレーザースキャナは情報通信施設やデータセンターといったICT装
置が多い建物には持ち込めないため、当面は全天球画像データが建物情報の一翼を担うと考え
ている。
既存建物に対する改修や修繕を行う場合、変更を加える箇所が元々どのように作られていたか
が設計に少なからず影響を与える。特に新築から長期間を経て何度も改修や修繕を加えられて
いる建物の改修では、設計者にはこれまでにどのような変更がなされたかを把握した上で、改
修の設計案の提示とそのための適正な工法の選択が求められる。このような場合、新築から現
在までに実施された工事の履歴情報が必要となる。一方、現況BIMは現在の状態を現すスナッ
プショットの建物情報となる。過去の現況BIMを参照することで、世代ごとの状況は把握でき
るが、そこには改修設計や工事概要の情報は搭載されていない。これらの情報は現況BIMとは
別に履歴情報とした方が管理しやすいことから、時系列的な設計・工事情報として管理を行う
ことした。
建築士法第二十四条の四により、建築士事務所は一定期間の設計図書の保管が義務付けられて
いるが、情報通信施設の営繕業務という立場から、当社ではこれらの設計図書を無期限に保管
している。保管は紙の図面だけでなく、マイクロフィルム化されている。近年それらをスキャ
ンデータとして整備し、ドキュメント管理システム上で検索・参照ができるような履歴情報と
して整備・運用している。これらの情報を現況BIMと連携させることで、設計者は過去の建物
の変更の経緯も把握することができる。もちろんスキャンデータの整備は紙図面保管品質だけ
でなく、データ化をする際に図面としての視認性や画像の歪みを徹底排除する品質管理が必要
となる。
建物ライフサイクルマネジメントで利用する建物情報は、上述の現況BIM以外の情報に加え、
現況BIMから抽出した属性情報のデータベース(特に複数の建物を経営資源として横断的に管
理する場合、属性情報は建物単位ではなく統合したデータベースとした方が活用範囲を広くす
ることができる)、物理的な建物とは必ずしも一致しない、取得単位で管理する減価償却をは
じめとした管財業務や有価証券報告書とも関連する固定資産情報、リーシング管理や清掃コス
トの積算、オフィスや事業スペースの管理情報、事業所税の算定で利用される各種スペース情
報、さらに建物や設備の性能諸元や業務のルールといったさまざまなドキュメント類が必要と
なる。これらは情報の粒度や考え方が異なるため、BIMモデルにすべて統合・集約するよりも、
それぞれのデータとして整備・管理し、共通の体系で情報連携を図ることが建物情報の管理と
して合理的となる。
このようにさまざまなデータを建物情報として管理し共有・活用するには、共通の管理体系で
さまざまデータを関連づけるとことから始める必要がある。建物ライフサイクルマネジメント
では、建物を大きくロケーション、敷地、棟といった階層で分類する。さらに詳細の情報を管
理する場合は、フロア、室……とドリルダウンしていけば良いことになる。重要なのは、これ
らの階層間でデータを正規化すること、それぞれにユニークキーとなるコードを付与すること
で情報を整理できるようすることである。管理対象となる建物数が多ければ多いほど、このよ
うな整理学で建物情報を整備していかないと管理が立ち行かなくなる。各種のコード体系で、
さまざまな形態の建物情報が連携されれば、横断的な情報検索・参照が可能になるだけでな
く、各種情報間の関連や相関関係の分析が可能となる。
情報通信施設の範囲であっても、規模や用途と建設時期でどのような工事が行われているか、
建物そのものにどのような特徴があるか、規模や種別だけではない事業ツールの視点からのク
ラスタリングができないか、といった検討は、データマイニングやテキストマイニングを手段
として整理できるのではないかと思う。また、その先には建物自体のラベリングや改修事例の
類似性、現況BIMモデルと全天球画像を比較した建物情報品質チェック、多角的視点からの中
長期建物活用シナリオ策定、といった視点でのAI活用があると考えている。このレベルまで
来て初めて建物ライフサイクルマネジメントにおける建物情報活用が実現した、と言えるよう
になるのではないだろうか。
GSA(U.S. General Services Administration:米国調達庁)が2011年にリリースした”BIM
Guide for Facility Management”では、BIMモデルを中心とした建物情報群を”Central
Facility Repository”に置き、FM導入前後から数年後までの段階的な建物情報の整備と利用拡
大のロードマップを規定している。内容は多少異なるが、長期的な建物ライフサイクルマネジ
メントやFM・維持管理を実践する上で、現況BIMを中心とした各種の建物情報を集約・連携
して利用できる建物データリポジトリ(リポジトリは一般的には容器や倉庫と訳されるが、IT
分野ではシステムに関する情報を保管・管理する仕組みを指す)の構築と継続的な進化、あわ
せて建物オーナー・ユーザーとの協働の場の実現が今後の課題だと考えている。