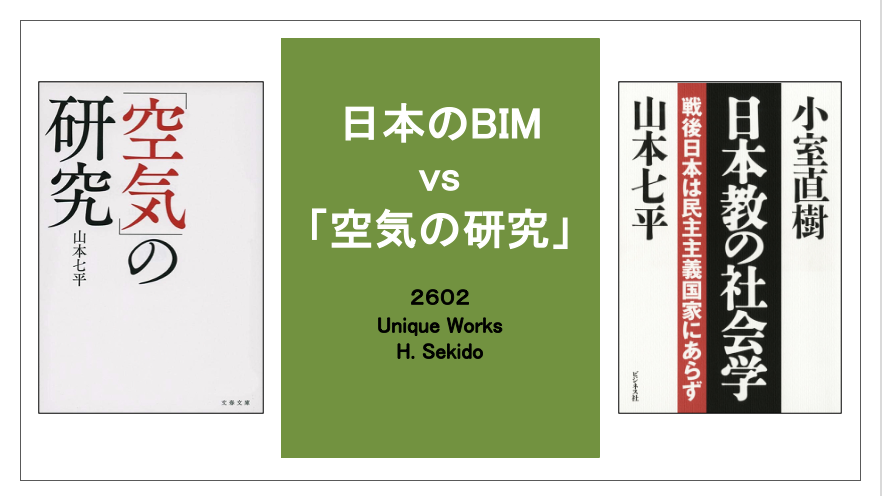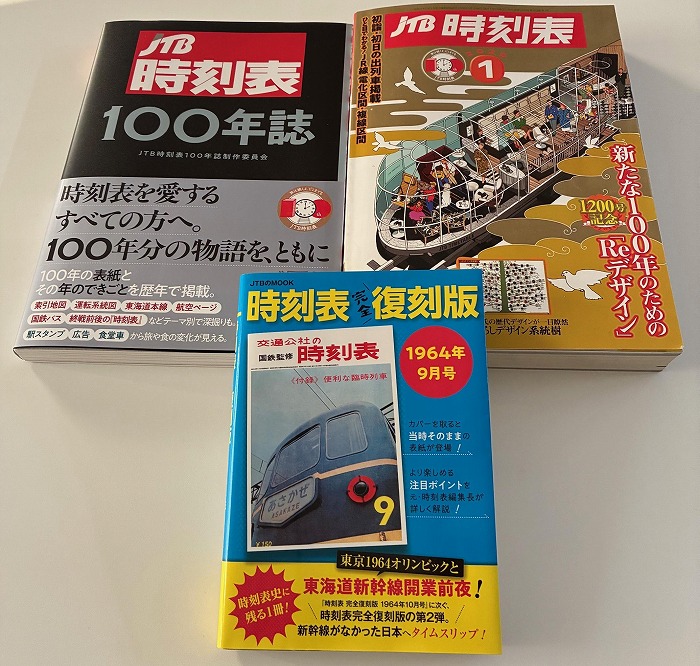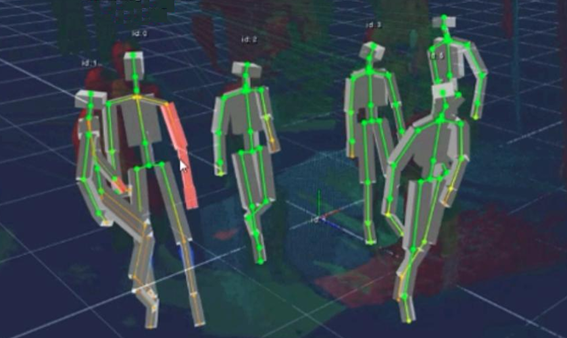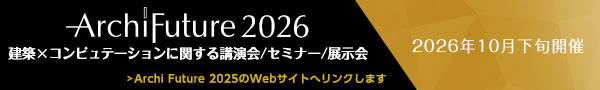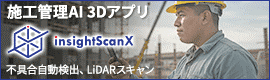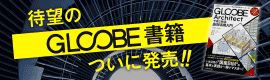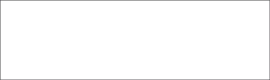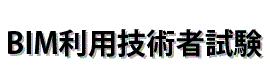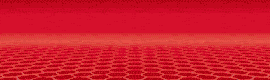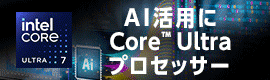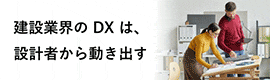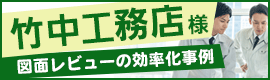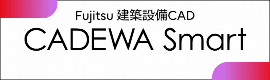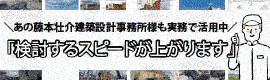![]()
データとしての現況BIMモデル活用考
~データマイニングからAIまで
2025.08.05
パラメトリック・ボイス NTTファシリティーズ 松岡辰郎
2025年7月に筆者が所属する「設計情報管理センタ」という組織の体制と役割が変わり、新た
に「FIMセンタ」と名乗ることになった。FIMとは”Facility Information Management/
Modeling”の略称(当社の造語?)であり、情報通信施設をはじめとする建物ライフサイクル
マネジメントにおいて、建物情報の整備と管理や活用のためのCDE構築、事業に資する建物情
報の提供に関するサービスを実施する。FIMのMはManagementの方が先に来る、というとこ
ろが特に重要なポイントだと思っている。
BuildingとFacilityの違いに明確な定義はないようだが、Buildingは建物のハードウェア、
Facilityは建物のハードウェア+ソフトウェアを包含する概念だと筆者は捉えている。建物を
事業やアクティビティのためのツールと考えると、建物ライフサイクルマネジメント全体で建
物情報を活用するには、建物をハードウェアだけでなくソフトウェアの視点からも分析・評価
しなければならないことがわかる。特に竣工後の建物運営とそれに伴う改修や大規模修繕と
いった設計・施工では、建物オーナーやユーザーがどのように建物を使用しているか、使用し
たいか、どの程度の信頼性と可用性を求めるかといった意思や方針、更に言えば価値観が十分
に考慮されているかが重要となる。
竣工後の建物運営における最も基本的な業務の一つである維持管理は、建物が当初想定された
要求性能を継続的に満たすための行為となる。建物のハードウェア性能を適正に維持すること
は勿論重要だが、その実現方法は稼働率をはじめとする可用性の要件や評価指標といった、建
物のソフトウェアの要件によって異なるものとなる。例えば、ある機器が累計運転時間の増大
や経年劣化により故障の確率が上がった時、故障による停止から回復する平均修復時間(MTTR:
Mean Time To Repair) の許容値によって、維持管理や点検の実施内容や評価項目は変わり、
そのための建物情報のあるべき姿と整備のための情報要求条件(EIR:Employer's Information Requirements)も異なるものとなる。例えば情報通信施設にも当てはまるが、故障による機器
の停止時間がゼロまたは限りなく短時間でなければならない場合、維持管理や点検時に故障を
予測する技術と情報が必要となる。もし、精度の高い故障予測が難しければ、常時監視と故障
時の即時切り替えが可能となる冗長構成が維持管理や建物整備の要求条件となる。
FMや維持管理はもとより企画や設計施工でも同じだと思うが、どのような建物オーナーや
ユーザー、どのような建物種別や建物運営においても、ここだけは譲れない、この部分だけは
護りたいという部分がある。建物に対する様々な要求条件からこの部分を明確にすれば、建物
ライフサイクルマネジメントにおける建物情報の整備と運用はかなりの確率で最適化できると
思う。
建物ライフサイクルマネジメントにおいて建物情報を整備する際、現況BIMは建物情報の主要
かつ中心的なデータとして位置付けられる。現況BIMモデルは建物を物理的に構成する部位・
機器の形状情報と、それらの性能諸元に関する属性情報を情報要求条件に基づく粒度と内容で
構成される。更に事業やアクティビティに関する情報や設備機器のメンテナンスや運転、各ス
ペースの利用状況といった情報を加えることで、建物オーナーやユーザーとも共有できる、
ファシリティとしての情報として利用することができるようになる。ここでもハードウェアと
ソフトウェアのどちらの観点から建物やその構成要素を見るかが重要になる。例えば、空調機
や電源装置はハードウェアの観点からは、何台あるか、どこに設置されているか、装置の性能
諸元はどうか、点検や修理の手順はどうか、といった情報が求められるが、ソフトウェア側か
ら見た場合、台数での評価というよりは、このエリアの冷却能力や空調容量はどのくらいか、
このスペースの電源容量はどのくらいか、といった情報の方がより重要となる場合も少なくな
い。こうして見てみると、建物をソフトウェア的にみると、スペースが重要な要素になること
がよくわかる。神はディテールに宿るのだとすると、建物オーナーの意思はスペースに宿る、
ということなのかも知れない。
建物をハードウェアとソフトウェアの両面から捉えることで、建物ライフサイクルマネジメン
トにおける現況BIMモデルは、点検・維持管理や経年劣化による大規模修繕だけでなく、建物
の現状把握や建物オーナーやユーザーが求める建物のあるべき姿とのギャップ、それに基づく
改修・修繕検討、更に設計BIMモデルの元データ等様々な場面で利用されるようになる。更に
広い範囲や業務で利用するためには、画像やデータといったBIMモデル以外の建物情報との連
携を考えれば良いだろう。
このようにして整備した現況BIMはそれ自体が複数のデータテーブルから構成される建物デー
タベースとしてみることができる。データベースとしてみると、アイディア次第で様々な集計
や分析ができるようになる。レンタブル比や共有と占有面積の割合といった基本的なものか
ら、その建物を使った事業における原価構成やランニングコスト比率、利用者一人当たりの種
類別コストから建物の材料の量や重さまで、データであれば様々な集計と分析ができるのでは
ないかと思う。
管理対象の建物が大量の場合や単数であっても規模が大きく多数の部位・機器を有する場合、
現況BIMモデルは単なる形状と属性の情報を統合したものではなく、横断的・面的な検索や集
計と分析ができる建物データベースとして機能するようになる。例えばある機器のあるロット
に危険な不具合があった場合、該当する機器を大量の建物から早急に探し出して対応しなけれ
ばならない場合を考える。図面から探す場合は何千という図面を人の目で見ながら探索をしな
ければならず、機器リストから探す場合は短時間で検索はできるが場所を図面にプロットしな
ければならない。複数の現況BIMモデルが建物データベースとして展開されていれば、検索と
配置位置の把握を迅速に行うことができる。これができたら、その次はその機器がどのような
建物に設置されている傾向があるか、とかどのような工事時に選定される傾向にあったか、と
いったことを分析してみると色々なことがわかるかもしれない。例えば、建物の部位・機器が
設置時から設置条件による劣化や故障の発生具合の傾向が分かれば、中期的な建物整備計画や
修繕計画の策定において、大量ではあるが在庫を抱えない段階的な調達計画を設定できるよう
になるのではないか、などと考えてみる。また、クレームと修繕の対応情報と背景にある建物
そのものの性能諸元や来歴情報を分析することで、ある不具合に対して、修繕で対応すべきか
抜本的な取り替えが有利かの判定精度を今以上に上げることが可能になるのではないだろうか。
現況BIMモデルが建物データベースとして活用できるのであれば、もう一歩進めてAIでの活用、
ということも考えていく必要があるだろう。ロジックや分析手法で結論を導き出せるものにつ
いては、AIよりもロジックや手法の方が信頼性と確実性が高いと考える。逆に言えば、従来の
ロジックや手法では解決が難しいものやパラメータが極端に多いものについては、統計・確率
の視点からAIを活用する価値がある、と言えるのではないかと思っている。そういう視点から、
現況BIMモデルから派生する建物情報をどのように学習させればこれまでにないような価値を
引き出せるか、を更に考えていく必要があるだろう。
建物ライフサイクルマネジメントでのAI活用について考える、というのは手段が目的化してい
ると思えなくもないが、汎用的な生成AIの活用ではなく、比較的特化した問題を解決するよう
なAIを構築する場合は、やはり問題設定が重要なのだと感じている。この問題設定のためのア
イディア出しと思考実験は色々やってみるとなかなか楽しい。例えば、既存建物の現況BIMモ
デルは改修工事の検討の情報として重宝するのだが、逆に建築以外のモノが書かれていないこ
とを問題としてみる。現地調査前の机上検討段階で既存建物内に建物オーナーやユーザーがど
こにモノを置いているか推論できれば、改修や修繕の基本検討の役に立つのではないか、と
いった仮説を立ててみる。次にどのようなデータを収集してアノテーションをしていけばうま
くいきそうか、を考える。このようにして実現性の高そうな問題だった
らPoC(Proof of Concept:概念検証)に進んでみても良いかも知れない。
この数年でBIMは建築生産だけでなく、維持管理を含めたFMやそれらを包含する建物ライフ
サイクルマネジメント全体で建物情報として利用できる、と認知されるようになった。しかし、
現状はまだ建物の構成要素のデータを集めて固めただけ、という感もある。データは個別に出
し入れするだけでなく、加工したり組み合わせたりすることでこれまでにない知見や価値を導
出する。現況BIMモデルはその可能性を十分に秘めていると考えている。