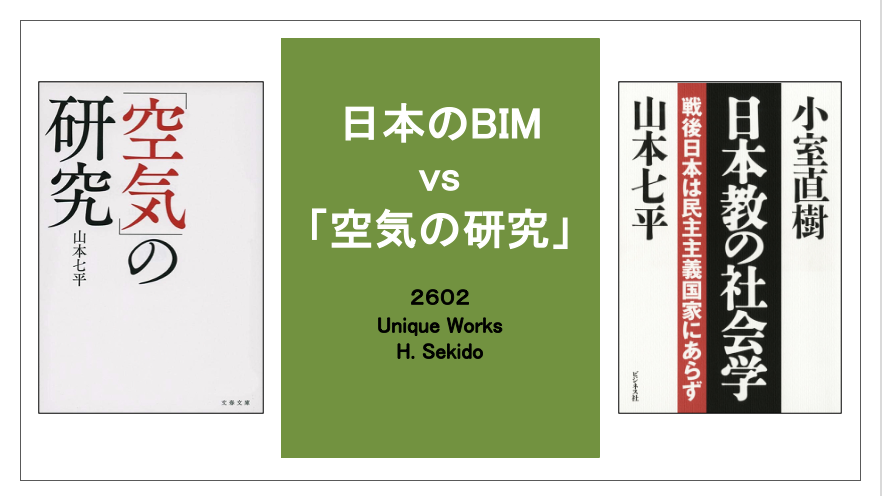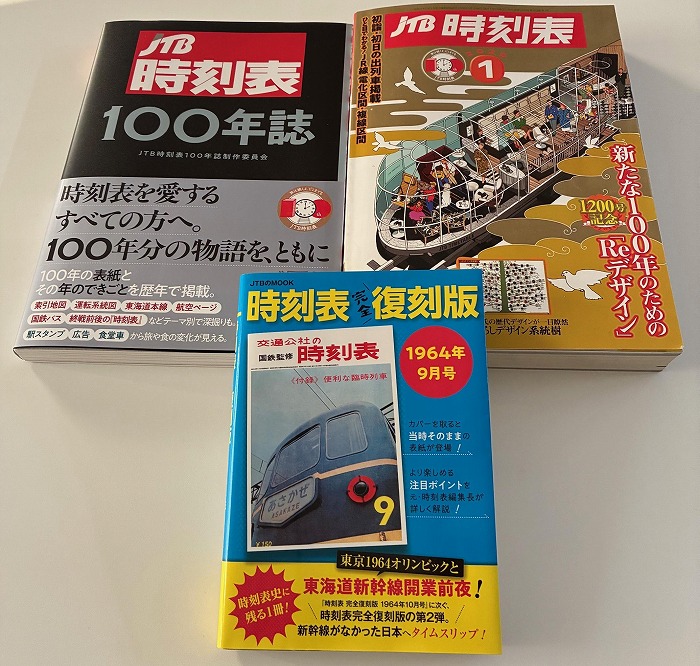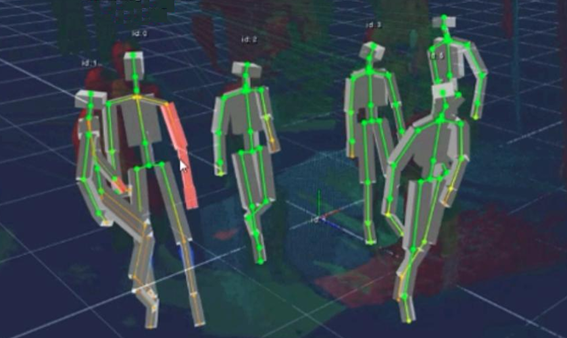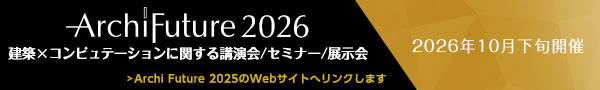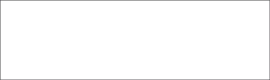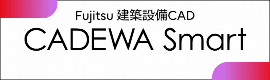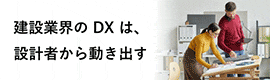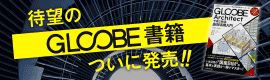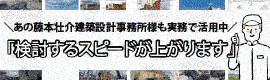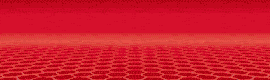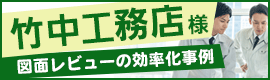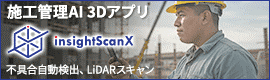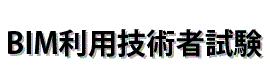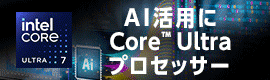![]()
木材利用偏重への疑問
2025.08.28
パラメトリック・ボイス 隈研吾建築都市設計事務所 名城俊樹
昨今、木材の積極的な利用が叫ばれ、以前と比較して多くのプロジェクトにおいてマスティン
バーの活用による二酸化炭素の固定が図られるようになってきた。
国土交通省をはじめとして、様々な公共建築においても木材利用を前提とした計画が建てら
れ、発注が行われている。その一方で、その流れに沿った法整備が行われているかというと疑
問が持たれる。公共物件の施設整備に関するベースとなる「国家機関の建物を官公庁施設の建
設等に関する法律」は徐々に改正が加えられているものの、未だに旧態依然とした庁舎建築物
のあり方を前提としており、今年改定された「木造計画・設計基準」についても十分な内容と
はいえない。計画通知の審査においても、過去の事例がまだ少ないことから適切な判断を下す
ことのできる公共機関の担当者が少なく、一般的な建物の審査でも相当な時間を要すことが多
い(今年から、計画通知の審査が民間の確認審査機関に開放されたが、民間での審査を想定し
ている公共機関、自治体はまだまだ少ない)。そして何よりも、予算が足らない。この2~3年
ほどで、設計を行っている現場の肌感としては建設費が50%以上上がっているように感じて
いる。これに加えて耐火木造等で木材を活用していくとなると、更に30%程度は追加で予算を
確保していただかないと計画が成り立っていかないと感じている。
ここ数年で急速に木材利用が推進されるようになってきたことから、現在は過渡期であるとい
え、こういった状況が発生しているものとは思われるが、その一方で現在のような木材利用推
進の状況がずっと続くかというと、個人的には少し疑問を感じている。
現在は木材利用を前提とすることによって様々の方面から予算を調達することが可能になり、
それによって木材を積極的に利用することが可能になっているという側面もあり、今後木材利
用が一般化していった場合はそう簡単には予算調達ができなくなってくるのではないかと感じ
ている。また、上記のような条件を満たすために実験的な側面で木材が利用されているという
ことも感じており、最終的には適材適所という形に落ち着いていくのではないかとも考えてい
る。そういった状況を俯瞰的に考えていくと、構造材としての木材利用に偏らず、もっと広義
の意味での木材利用を推進していくべきではなかろうか。構造材と比較して、仕上材や什器に
ついては使用される材積が極めて小さくなるが、多くの中規模物件においてはまだまだ木材を
主構造として設定することが難しいという側面もあり、また一般的な耐火木造方式では木材が
露出しないことも多く、視覚的な観点からも仕上材や什器への活用が重要になってくる面もあ
る。
世界的にこの20年で木造技術は急激に進歩を遂げ、日本においても3Dモデルからダイレクト
にプレカットを行い、現場の組み立てにおいてもARを活用する等、技術面における木材利用
の環境はかなり整ってきたといえるだろう。そういった中で、偏った視点でない法整備、予算
計画等がますます必要になってきていると強く感じている。