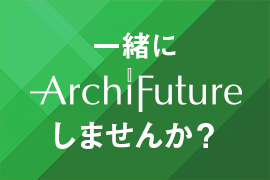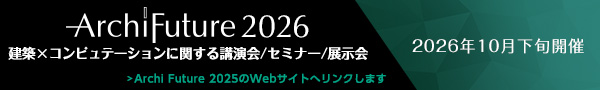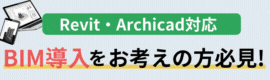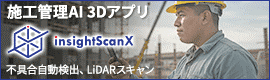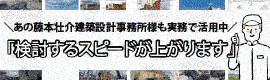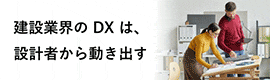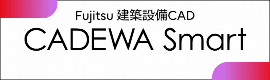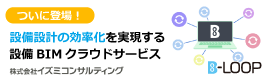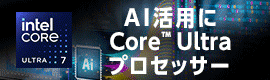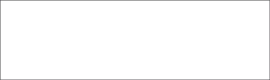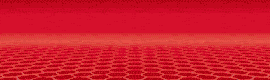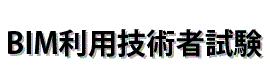![]()
インターンシップと「BIM職」の採用について
2025.10.21
パラメトリック・ボイス 前田建設工業 綱川隆司 画像は前田建設工業 建築設計部門インターンシップ募集のサイト(今期募集は終了)。
記録的な暑さが続いた9月が終わり、ようやく秋らしくなってきた10月2週目にこのコラムを
書いています。夏の終わりといえば学生インターンシップです。例年8月下旬から9月中旬に
かけて学生インターンシップを受け入れています。これまでの「申し込みの入口が分からな
い」、「御社で何が体験できるのか分からない」というご意見を受け、今年は夏期休暇前に建
築設計部門のHP上に学生インターンシップ募集のページを設けました。特に事前アナウンスも
せず限られた短い期間の掲載だったにも関わらず、我々の想定を大幅に上回る応募がありまし
た。受け入れ側のキャパシティーの問題もあり、結果的に多くの学生の方にお断りのご連絡を
することになり大変申し訳ありませんでした。今回の反省を踏まえて次回以降はエントリーの
仕組みを再考いたします。
今回の件を通して認識を改めたことがあります。以前はインターンシップとは学生が「企業で
の就業体験を行う」ことであり、企業の採用活動とは一線を引いていると私は考えておりまし
た。しかし文科省・厚労省・経産省の「三省合意」とやらが改正され、一定の条件を満たすイ
ンターンシップ(タイプ3・4)では企業はそこで得られた学生情報を採用活動に活用できる
ようになったそうです。ちなみにタイプ3とは対象は学部3年~修士2年の汎用的能力・専門
活用型インターンシップで短期5日間以上長期2週間以上、タイプ4とは対象は修士~博士の
高度専門型インターンシップ(試行)で2か月以上の長期のようです。すでにインターンシッ
プが採用の前哨戦的な位置付けととらえる学生も多いようで、確かにそれならば真剣にもなる
でしょう。インターンシップを経由して採用ならば、学生側にも企業側にも相互にミスマッチ
を回避できるメリットはありますが、採用選考が長期化する可能性も否めないと思います。
今回のインターンシップについては、あくまで就業体験の枠を超えないと私自身は整理して
います。
結果的に私の設計戦略部では例年より多めの4名の学生を受け入れました。彼らがインターン
シップで何を体験したかったのか目的はまちまちで、アンケートでのインターンの目的を拾っ
てみると「木造・木質構造」「AI活用事例」「設計の過程を知る」「海外コンペの仕組み」と
四者四様でした。この対象領域のバラエティは設計戦略部の特徴でもあり、異なる専門性を
持った人材を集め、技術開発と実物件への実装を両輪でやってきました。学生にも直接申し伝
えましたが、我々はゼネコン設計部のサンプルとしてはあまり相応しくないかもしれません。
以前はBIMについて興味を持ってインターンを申し込む学生が多かったので、当時とは少し様
相が変化した感があります。インターンシップ開始前にソフトウェアの習熟度については確認
をしますが、最近は既に何かしらのBIMソフトウェアを習得している学生が多いです。これは
とても良い傾向だと思いつつ、たまたま私のところに来る学生がBIMの得意な人たちに偏って
いるのかしらと気になり、いつものようにCopilotに「大学におけるBIM教育」について質問
してみました。
その回答は要約しますが、「日本の大学におけるBIM教育には大学間で大きなばらつきがある
ことは前提として、一部の進んだ大学ではシラバスでBIMを謳っているが、多くの大学では概
念的な教育にとどまり学生の自主学習に頼っており、『BIM教育はもっと実践的であって欲し
い』という学生のニーズに関する論文がある」、と紹介されました。企業側でBIM人材が不足
していることは以前からの調査で分かっていますが、今後もBIM人材不足は大きなブレーキに
なりそうです。
国内の主要な建築系大学別のBIM・ICT・DX教育に関する比較表も作ってくれましたが、一部
の先進的な大学を除くと大学院或いは研究室単位での指導に限定されていると言えそうです。
少し目線を変えて海外建築系の大学の比較表をお願いしてみました。明らかに国内の比較表よ
り内容が濃い。特徴としてはロボティクスとデジタルファブリケーションなど生産領域での
テーマが多いことに気が付きます。
フムン。ここのコラムで最後は海外の脅威に辿り着くケースが最近続きましたが今回もです
か・・・。自動化・省人化が果たせる建築生産の変革をゴールと据えたときに、どのような人
材が必要なのか、どのような教育を施せば成るのか、産官学で一緒に考えないとこの業界の
先行きは暗いと感じました。タイトルでは「BIM職」と表記をしましたが、BIM人材を今後ど
のように育成し実務に携わる場を用意するかを掘り下げる必要性があるでしょう。企業側も
どのような人材を求めているかを職能・職域でより細分化し明示する必要があるかもしれませ
んね。
過去にその一部の先進的な大学のある先生から「いつまで企業は時代遅れの手書きの即日設計
を入社試験に課すのか?」と指摘を受けたことをなぜか今思い出しました。
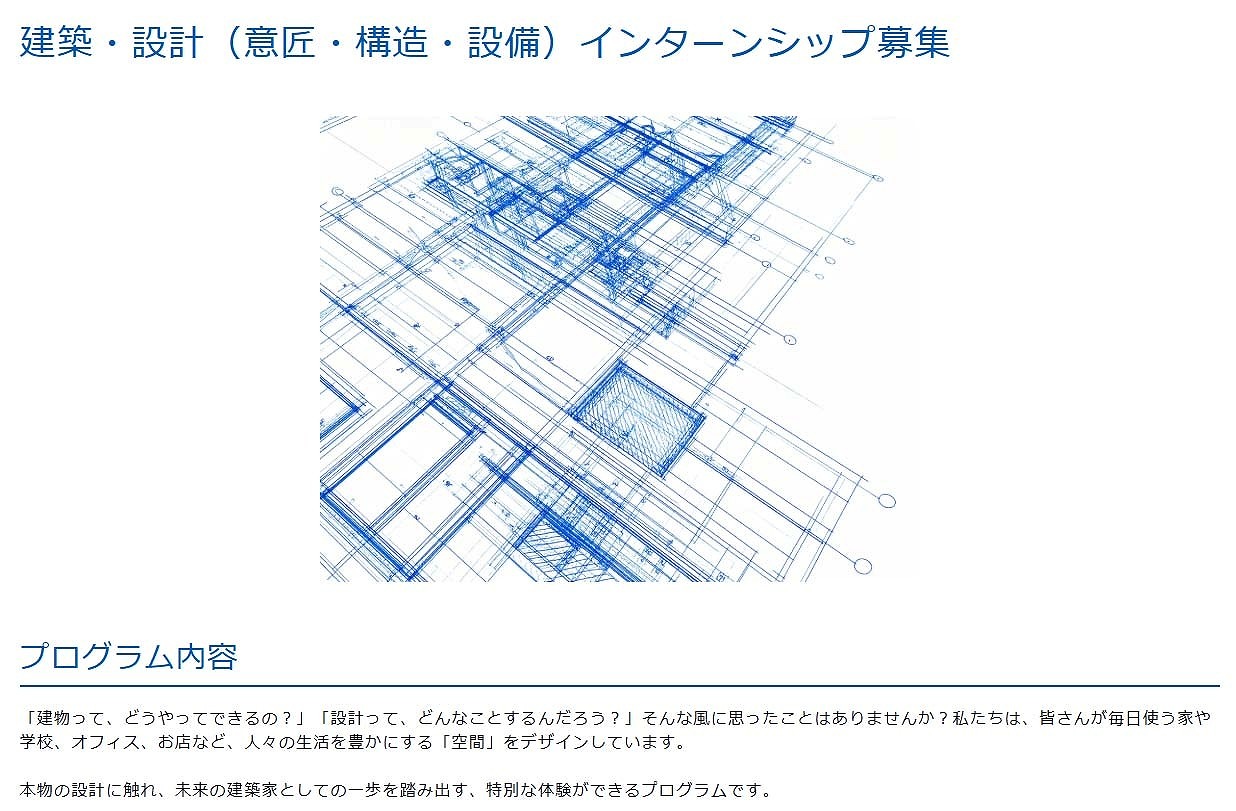
※上記の画像、キャプションをクリックすると前田建設工業のWebサイトへリンクします。