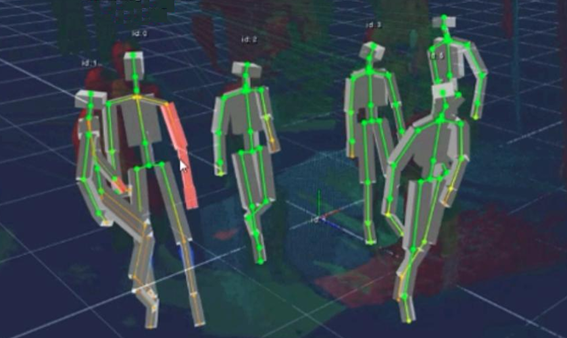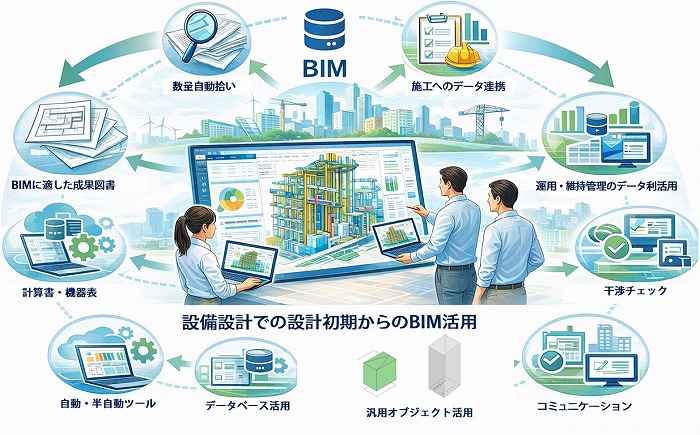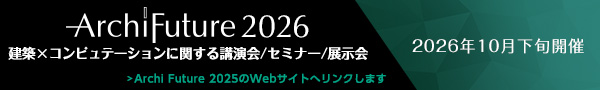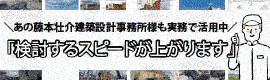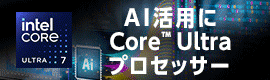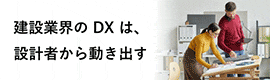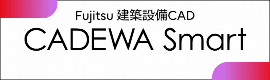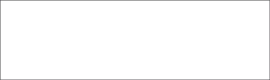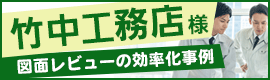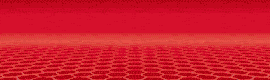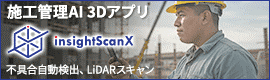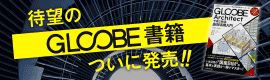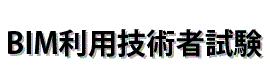![]()
おいらひとりで てつがくするのニャー
2025.07.10
パラメトリック・ボイス 竹中工務店 / 東京大学 石澤 宰

先日誕生日を迎えて44歳になりました石澤です。
こちらに私がはじめてArchiFuture Webに掲載したコラムがあります。このウェブサイトでは
肩書が更新されていますが、当時33歳だった私は現場設計室配属の設計部員で、他の錚々たる
執筆陣に囲まれて震えながら書いたコラムでした。今回で11年目に突入し、タイトルにニャー
スのうたの引用をつけられるくらいには慣れてまいりました。初対面と思いきやこのコラムを
お読みくださっている方にお会いする機会も多く、ありがたいことです。
ちなみに、10年間ってまあまあ頑張ってる方じゃない?と一瞬思いましたが、ニャース初登場
のポケットモンスター 赤・緑(1996)から来年で30周年でした。すみません、(2015~)ご
ときが調子に乗りました。今後も地道に書いていこうと思います。
先日、所属する研究所で「10年後の研究の未来像アンケート」というものがありました。
10年前を振り返りつつ、では同じタイムスパンで10年後を考えたとき、私にとっての研究の
未来像をひとことで示すと何になるか。この問いへの私の答えは「記憶する壁、歌う床、怒る
天井」というものになりました。
ああ、この人は建築が好きすぎてついにIfcFloorからニャースのうたが聞こえてくるように
なったのか……と思っていただいた方もそれほど間違いではないのですが、もう少しこのトン
チの裏には経緯があるので、少しそれについてお話してみたいと思います。
先般「生産研究」に掲載された研究速報は、設計はされたが建たなかった建築、いわゆるアン
ビルトの建築情報モデル化についてのものです。現存する建築のモデル化も大きな問題である
一方、これまで存在したが滅失した建築、あるいは実現しなかった建築もまた情報アセットで
あり、これらを活用することもまた重要な課題です。
アンビルトに限らず、図面をもとにモデル化するときには必ず、図面に描かれていない部分の
解釈が必要になります。設計者がいれば確認できますが、そうでない場合はモデル作成者が都
度判断するしかない。他の納まりから類推したり別な建築を参照したりなど、その解釈・判断
はかなりの量に上るのですが、図面やモデルにはそうした情報が残されないのが通例です。
一方、私達の創作物は、それが芸術的な大作であれちょっとしたメモ書きであれ、時間が経て
ば文化的遺産になり得ます。これを、「物質的知的文化のコミュニケーションの理解に関係す
る人間の活動のすべてのドメイン」が文化遺産である、と定義するのがLondon Charterが
2006年に発行した「ロンドン憲章」です。古かろうが新しかろうが、珍しかろうがありふ
れていようが、私達のありとあらゆる活動の痕跡は文化遺産の範疇に入る。ロンドン憲章はこ
れをコンピュータによりビジュアライズすることを念頭に置いたものですが、その際に「人間
がデータオブジェクトの理解と解釈をするプロセスについての情報」もまた残されるべきであ
るとし、これをパラデータ paradata と定義します。
比較的よく聞くメタデータ metadata と似ているのは、どちらも「データのためのデータ」
であるという点です。メタデータはそのデータ自体に関する情報、たとえば作成者や変更日な
どであるのに対し、パラデータは例えば、根拠となる図面などの解釈の方向性や、その時に使
用した方法論についてのメモなどが挙げられます。つまり、そのデータを一つの結論に収束さ
せるために必要となった様々なプロセス(言い換えれば、なぜ他の解釈を採用しなかったかに
ついて)について述べるのがパラデータだと言えます。
BIMにこうした情報を与えておくことはさほど技術的に難しいことではありません。しかしこ
れまでは、このような情報の入力には標準化が先立つ必要があり、どんな情報が書かれるべき
かを先に網羅しなければ入力ができない、という状況に陥りがちでした。こうした情報を標準
化する動きも注目すべき重要な動向である一方、過度な標準化はデータ作成コストを高くし、
現実性を損ねる(まあつまり、作っていてイヤになる)ことにも繋がります。
しかしここに昨今のAIが組み合わさると状況が少し変わってきます。これまで情報とは、情報
処理に向いた形、いわゆるマシンリーダビリティの高い形に整備するのがよいと考えられてき
て、その利点は今でも大きくは変わりません。しかし、人間の理解に沿った言語の処理も近年
急速に容易になってきて、ヒューマンリーダブルなデータであっても処理の対象にぐっと近づ
いてきました。
このような状況であらためて私達の身の回りを見渡してみると、私達が日々建物で経験するこ
とは山のようにあるのに、ほとんど何も記録されていないということに気づきます。照明が切
れている、お湯が出ない、火災報知器が誤作動した、そういう類の不具合は修繕とともに記録
されることもあります。しかし、部屋で突発的に行われた楽しいパーティ、盛況に終わった発
表、リノベーションで人が集まるようになったシェアドスペースについて、位置情報や生体情
報でそれらを伺うこともできますが、そもそもそうした出来事について、話され、人々が記憶
したことは、建物の側にはあまり残りません。
秘境駅と呼ばれる、乗降客のきわめて少ない駅には、その訪問者が時間を超えてコミュニケー
トするための「駅ノート」が置かれていることがあります。ギャラリーや展示会の芳名帳など
のようでありながらまたひと味違っていて、「はじめての秘境駅です」「孫と来ました」「創
作の題材にしたいです」「歩いてきました(←私:どうやって!?)」のように、人の心をく
すぐる何かがそこにはあります。
仮にそうした情報が建築と共に残るとしたら、その残す先は建築そのものしかあり得ない。そ
して、その建築がたずさえた様々な情報と会話ができるようになるとしたら、その先には何が
あるでしょうか。
私「ねえ、このマンションの住人ってもしかして昔、猫でも飼ってた?クローゼッ
トの奥に引っかき傷みたいなのがあるんだけど」
壁「あ、気づきましたか。前の前の住人の時ですかね、いましたよ。4匹」
私「明日の夜台風が直撃するかもしれないってさ。どうしようかね」
窓「洋室の窓はこのまえ直しましたからいいですけど、玄関横のジャロジー窓は何
かで塞いでおいたほうがいいかもですね。以前お子さん、なんか靴が濡れてるっ
て言ってましたけどたぶんそれですよ」
私「家族も成長したし、そろそろ間取りを変えようかと思うんだよね。ここの間取
りって動かせる?」
床「うーん、どうでしょうね……壁量はバランスですからね。設計の方に聞いたほ
うがいいかもしれませんよ。私はリノベしてまたリフレッシュできるの歓迎です
よ!これからもご一緒したいですからね♪」
私「あーごめんなさい、やっぱりこの火災報知器の位置こっちに合わせて……」
天井「何べん穴開けんねん!だから天伏は早く描かんかい!」
私にとっては、建築を対象に研究をしていて、ある研究が面白くなっていくとしたら、それは
私の力である以上に、その建築が面白いのだろうという気がします。市井の人の普通の暮らし
の裏にも必ず聞き手の心を引き付けてやまない話があるように、どんな建築にもそうした想い
はあって、それらと親しみよりよい関係を築くという大きなゴールは、建物を作る人間として
も、建物について考える人間としても、目指していきたいものだと思うようになりました。
ポケットモンスターの世界では人々に相棒のポケモンがいますが、現実世界の私達にも相棒と
なる建物はいます。不動産屋で「キミに決めた!」だと今はちょっとヘンな人ですが、長く付
き合う建物がそのような存在である未来から見えるものもあると思っています。しゃべるポケ
モンといえばニャースですね。というわけで冒頭のタイトルにようやく戻ってこられました。
という、こういうことはChatGPTとすごい量の雑談をするようになった今だからこそ思いつ
く話ですが、10年前に考えていたこととうっすら繋がってもいて、10年後にはこれそのまま
ではないにせよ、何らか「建物の人となり」がわかるような未来に向かって進んでいけるとい
いなと思っております。
ちなみに私は文字でのAIチャットで立ち現れてくる人格は好きなのですが、音声会話にすると
どうにも違う人のような気がして不思議に思っています。建物にどんな声をまとわせるべき
か。私の周りを見渡してみてもまだそれっぽい声は聞こえてきません。やっぱり年齢相応に渋
みを増した声がいいのか、永遠に若々しい声がいいのか、水田わさびさんとか犬山イヌコさん
みたいなキャラクターの声がバチハマりなのか……。
あ、そうだ。人間と建築のインターフェイス構築に適した声優についての考察、みたいな研究
に予算がつく未来が一番の希望でした。お金も大事です。