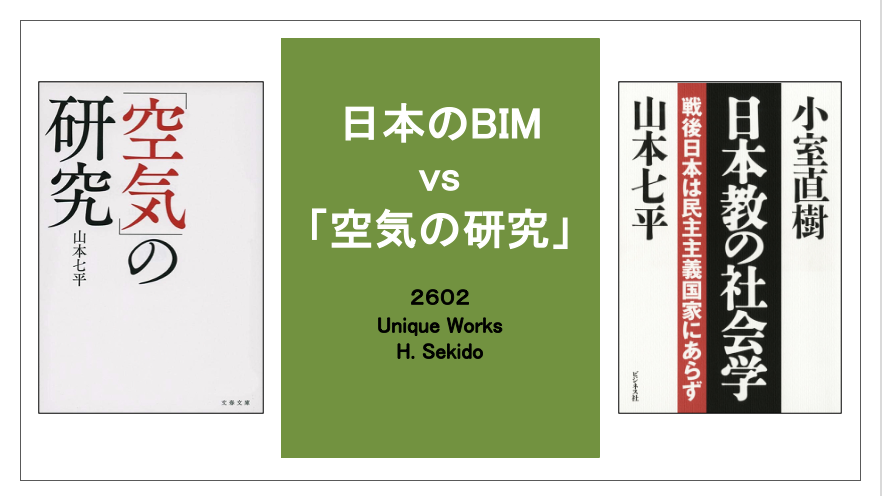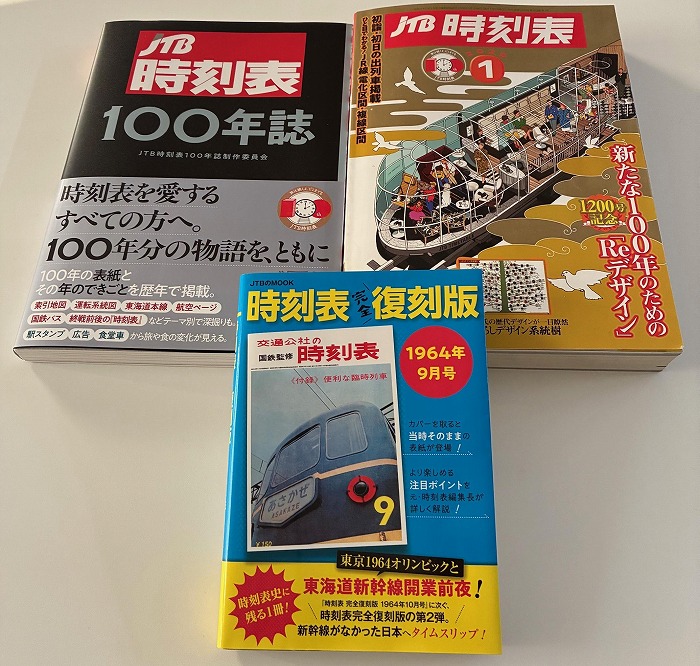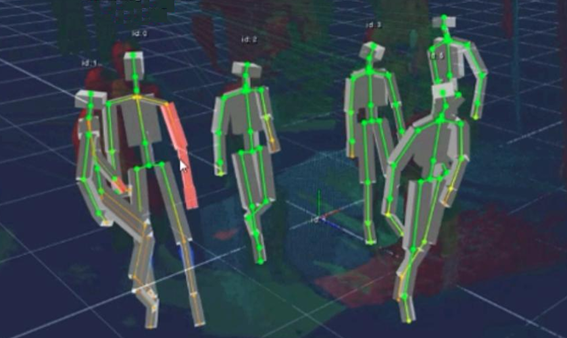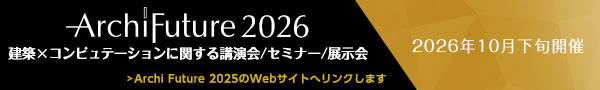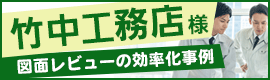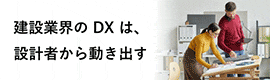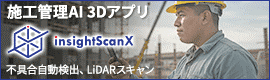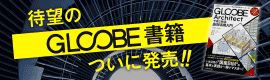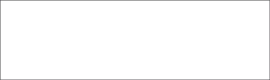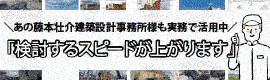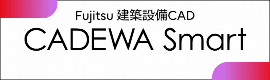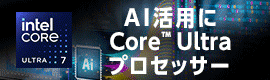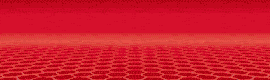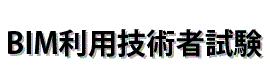![]()
情報は流れて初めて価値になる ─ AIと建設業
2025.10.07
パラメトリック・ボイス 三建設備工業 日比俊介
建設業界では、毎日膨大な情報が生まれている。議事録、見積書、図面、日報、計画書…。
しかし、その多くはプロジェクトが終わると同時に止まってしまう。これまで建設業が「毎回
ゼロから始める産業」と言われてきたのは、情報が循環していなかったからではないだろうか。
他の業界を見ると、製造業は製品のライフサイクル全体をデータでつなぎ、小売業は購買履歴
を即座に物流や在庫に反映している。情報が循環することで、効率化だけでなく、新たな価値
も生まれる。しかし、建設業は依然としてプロジェクトごとに情報が閉じ、縦にも横にも流れ
ていかない。その結果、似たような課題やトラブルを繰り返し、生産性が向上しない。
ここにAIという視点を加えると、話は変わる。AIはデータが流れれば流れるほど賢くなる。も
し情報が循環していれば、AIはそこからパターンを学び、次のプロジェクトに提案できるよう
になる。たとえば、設計段階で「この設計変更は過去にも繰り返され、結局修正が必要になっ
たケースが多い」と教えてくれるかもしれない。施工段階では「このやり方は手戻りを招い
た」と警告を出してくれるだろう。設計で見逃された問題も施工で補正でき、逆に施工で苦労
した知見が設計に戻って次に活かされる。これこそ、情報が循環することの意味だ。
先日参加した「Autodesk University 2025 (AU2025)」でも、この流れが示されていた。設
計、施工、運営までをAIネイティブな環境でつなぐ新しいクラウド型プラットフォームが発表
され、従来の設計ツールとデータをシームレスに共有するデモも公開された。これにより、情
報の断絶がなくなっていく可能性が見えてきた。
また、AIアシスタント機能が設計ソフト上で自然言語によるプロンプトに応答する形に進化し、
タスクの自動化や設計レビュー、照明・ファサードの分析などへの応用が報告された。これに
よって、過去の経験や設計意図がデータとして蓄えられ、AIがそれを解釈して現場へフィード
バックする情報循環のループが、実務レベルで動き始めている。
さらに印象的だったのは、設計の初期コンセプトから詳細設計までをつなぐ新しいAIモデルだ。
テキストや質感、物性といった条件から建築モデルを生成し、それを人間が修正・活用するこ
とで、デザインの効率と品質を両立できる。これもまた、情報が循環し、AIが学習のサイクル
に参加する良い例だ。
これらの発表を見て、情報の循環は、すでに現場を含む業務プロセスに変化を起こし始めてい
るのだと強く感じた。ツールがクラウドとAIベースになり、データ構造が整理・共有されるこ
とで、知見のロスが減り、意思決定が速くなる。
もちろん、すべてが完成形ではない。プロジェクトごとに条件が異なるため、AIが提案する設
計や配置がそのまま使えるわけではなく、人間の経験と判断は不可欠だろう。また、データの
品質や更新頻度、ツール間の互換性といった課題も残っている。
この動きを建設業界全体で加速させるためには、いくつかの視点があるように思う。
まず、ライフサイクル全体を通じてデータを活かす仕組みが不可欠だ。設計から施工、維持管
理といった「縦の情報循環」を確立すること。AU2025で紹介されたクラウド型設計プラット
フォームと既存ツールを連携させるモデルは、この方向での循環を現実のものにしている。
そして、あるプロジェクトで得られた知見を他プロジェクトで速やかに共有する「横の循環」
も重要だと感じる。設計での不具合、施工での工夫、現地での気づきといった情報は、業界全
体にとっての財産となる。AIアシスタントやクラウド型のデータマネジメント機能がその役割
の一端を担い、自然言語での対話を通じて情報にアクセスできるようになれば、職人や設計者
にとっても使いやすい環境になるだろう。
これらの循環を実現するには、共通基盤が重要だ。AU2025で示されたように。AIネイティブ
なクラウドプラットフォーム群や、ツール間・データ間をつなぐ新しい接続プロトコル(MCP:
Model Context Protocol)が、この共通基盤に相当する。これが整えば、情報は散らばること
なく、価値を生み出す形で循環する。
ただし、本当に大切なのは個別のAIツールに留まらないこと。図面チェックや工程シミュレー
ションにAIを活用する事例はすでに点としてあるが、重要なのは、情報が部門間を循環する
ループを構築することだ。
これまで、各社が苦労して集めてきた情報は、流れる仕組みを持つことで初めて“新しい資源”
に変わる。AIはその流れを加速させ、そこから学びを引き出すことで、業界全体を押し上げる
力になる。プロジェクトは毎回、条件も制約も異なる。だからAIがすべてを自動化することは
ないだろう。
しかし、人間の柔軟な判断とAIの再現性が組み合わされば、確実に前進する。ベテランの直感
を、AIが過去のデータで裏づける。逆にAIが提案した設計案を、現場の経験が微調整する。
こうして人とAIが補い合えば、精度もスピードも、これまでにないレベルに達するはずだ。
この協働を支えるのが、個別のシステムを超えて情報をつなぐ共通基盤だ。設計、施工、調達、
経営とバラバラだった情報が一つの流れに乗り、循環する。プロジェクトが終わるたびに学習
が蓄積され、次のプロジェクトがよりスムーズになる。その積み重ねが、業界全体を押し上げ
る力になる。
日本の建設業にとって、人材不足や多層下請けによる分断は、避けて通れない課題だ。だから
こそ、情報を循環させ、AIがそれを学び、人と一緒に判断する仕組みが必要になる。海外では
すでに動き始めている。日本もこの流れを取り入れれば、経験の断絶を乗り越え、持続的に進
化できるはずだ。
情報は流れて初めて価値を生む。そしてAIはその流れを加速させる。建設業を「経験産業」か
ら「学習産業」へと変える可能性は、決して低くはない。今つくるべきは、情報が流れ、学び
が積み重なり、次の挑戦につながる循環の仕組みだ。その先には、人とAIが協働して成長して
いく、新しい建設業の可能性が広がっていると感じている。