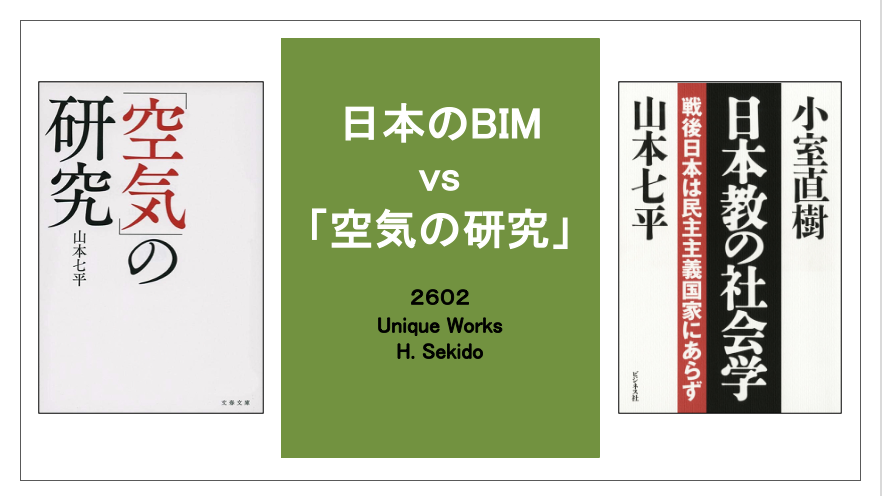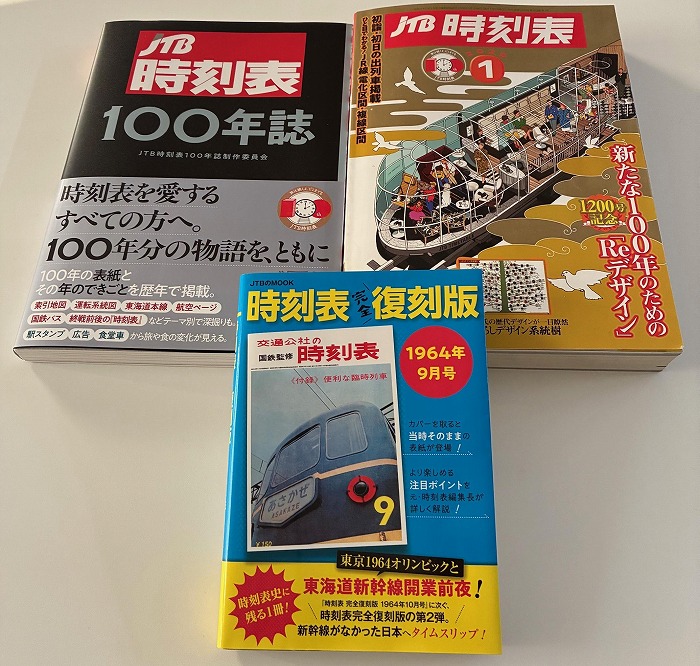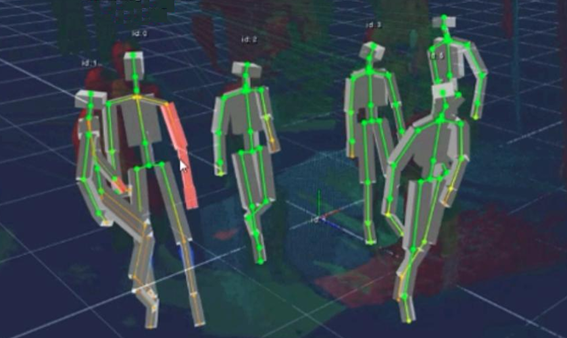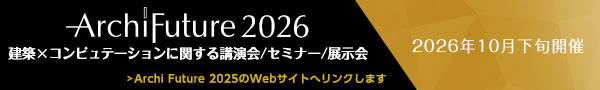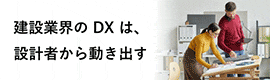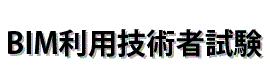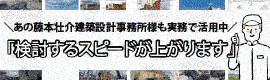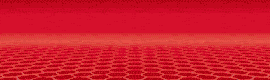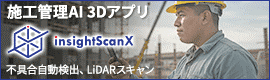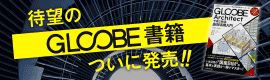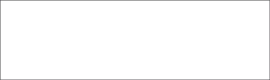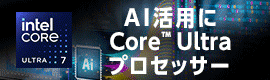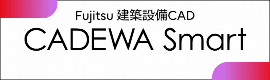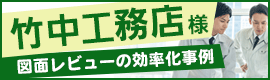![]()
大阪・関西万博 2025 マレーシア館
2025.10.30
パラメトリック・ボイス 隈研吾建築都市設計事務所 松長知宏
大阪・関西万博が閉幕しました。半年にわたって開催された大きな祭典が終わり、いま多くの
方がそれぞれの立場から振り返っていることと思います。私自身も、弊社が設計・工事監理を
担当したマレーシア館のプロジェクトに関わらせていただいたご縁から、この場を借りて少し
ご紹介したいと思います。
このプロジェクトが始まったのはおよそ3年前。当時はまだデザインの方向性を模索しており、
パビリオンのテーマである「Weaving the Future in Harmony(調和の中で未来を紡ぐ)」
をどのように建築として表現できるかを探る段階でした。未来を感じさせながらも、マレーシ
アらしい温かさを持った建築を目指し、何度もスタディを重ねていたのを思い出します。
建物の顔となる素材には、マレーシアと日本の文化をつなぐ象徴として竹が採用されました。
自然素材でありながら施主からのリクエストでもある「futuristic(未来的)」な印象をどう
表現するか——これがデザイン上の大きな課題でした。竹を整然と並べて使うと、どうしても
“和風”な印象が強く出てしまう。そこにマレーシアの躍動感や柔らかさをどう重ね合わせるか
を探る中で、今回もグラスホッパーなどのコンピュテーショナルデザインが大きな助けとなり
ました。
設計では、三次元上で正確にモデリングを行い、各部材に番号を付けてパラメトリックに制御
していきます。ただ、今回はそこに一つだけ「ゆるさ」を加えました。つまり、部材の位置を
厳密に固定せず、ある程度の誤差を許容するように設計したのです。竹というばらつきのある
自然素材の特性を考えると、その柔軟さを受け入れる方が、結果的に施工性も高く、全体とし
て自然な表情に仕上がりました。
たとえば、竹の取り付け位置は「分数」で指定しました。5000本を超える竹を現場で取り
付けるには、下地を等分して割り出す方法のほうが正確で早いことが分かったのです。3D
データの中では、すべてを完璧にコントロールしたくなりますが、実際の現場では素材の個体
差や職人の勘が生きる“余白”が必要です。デジタルとアナログの狭間で、そのバランスを取る
ことこそが、今回の経験で最も印象に残りました。
万博というのは、本当に途方もないスケールのイベントです。一つのパビリオンだけでも、デ
ザインから施工、国をまたいだ調整に至るまで、数え切れないほどのドラマがありました。
それが150以上の国と地域によって構成されているのですから、その背後にあるコミュニケー
ションと努力の量は想像を超えます。
半年という短い会期を終え、関わった建築が解体されていくのを見るのはやはり寂しいもので
す。それでも、竹の再利用をはじめ、そこで得た知識や経験を次のプロジェクトにつなげてい
くことが、まさに未来を「紡ぐ」ことにつながるのではないかと思っています。